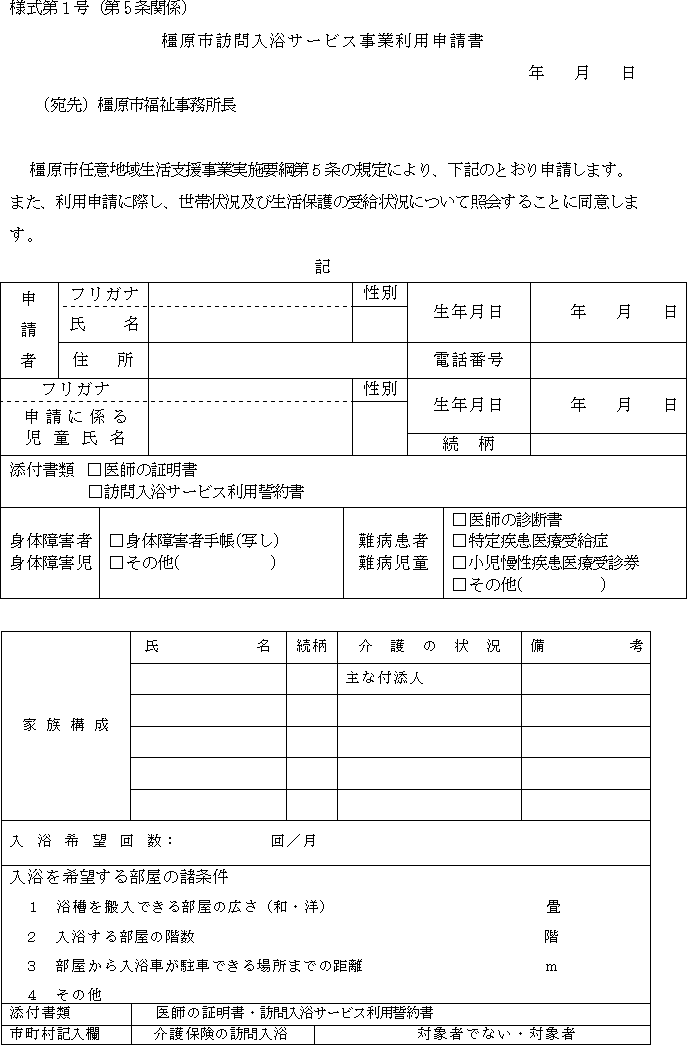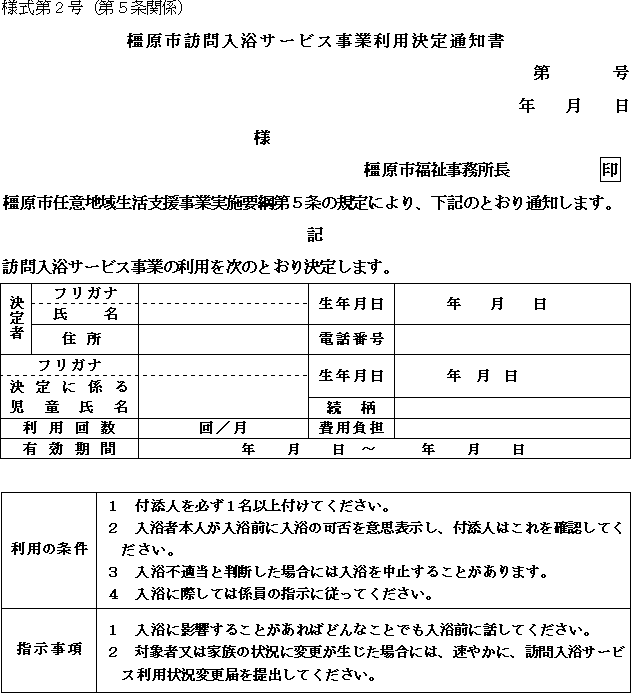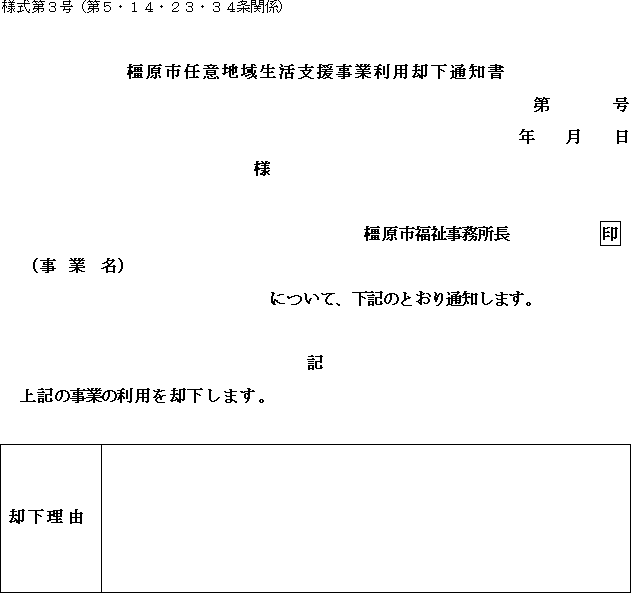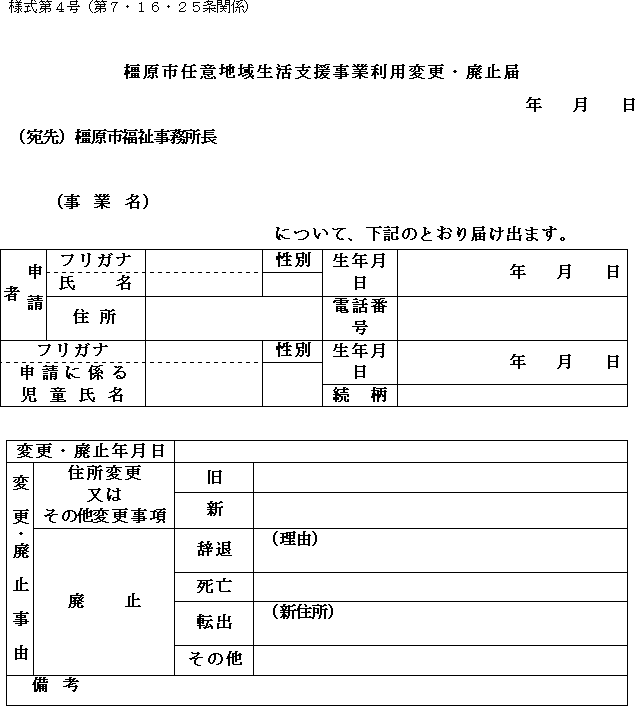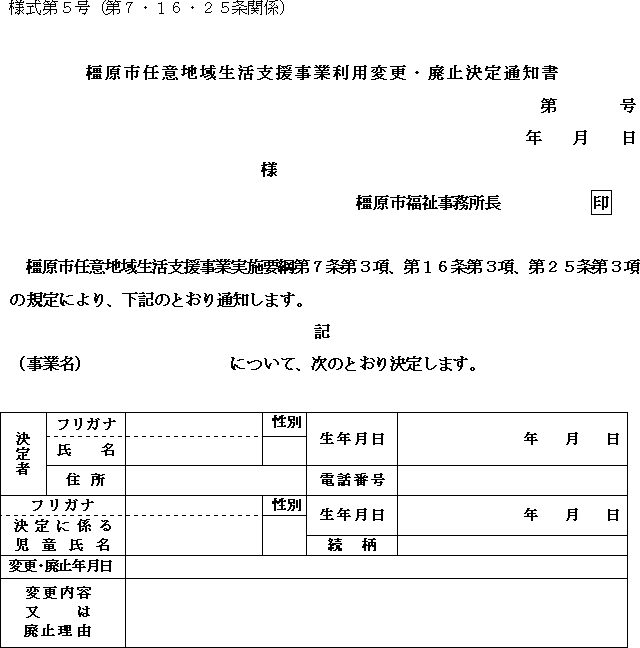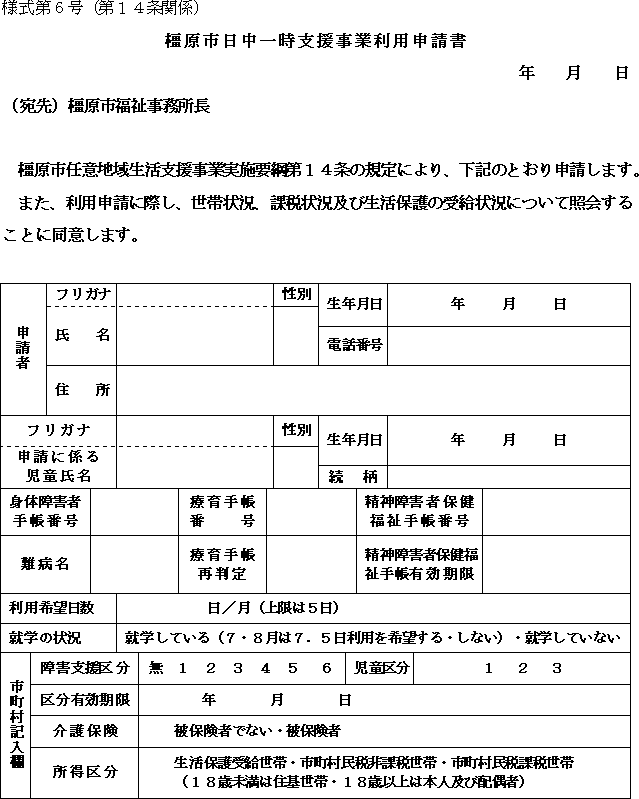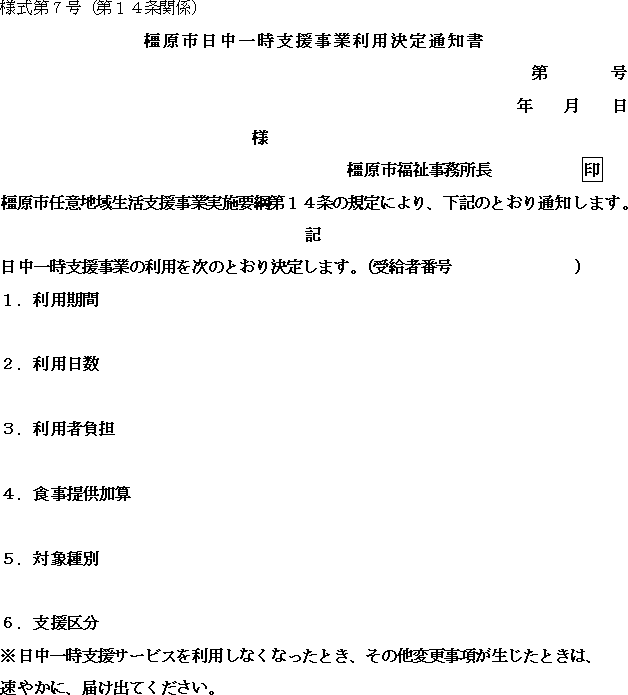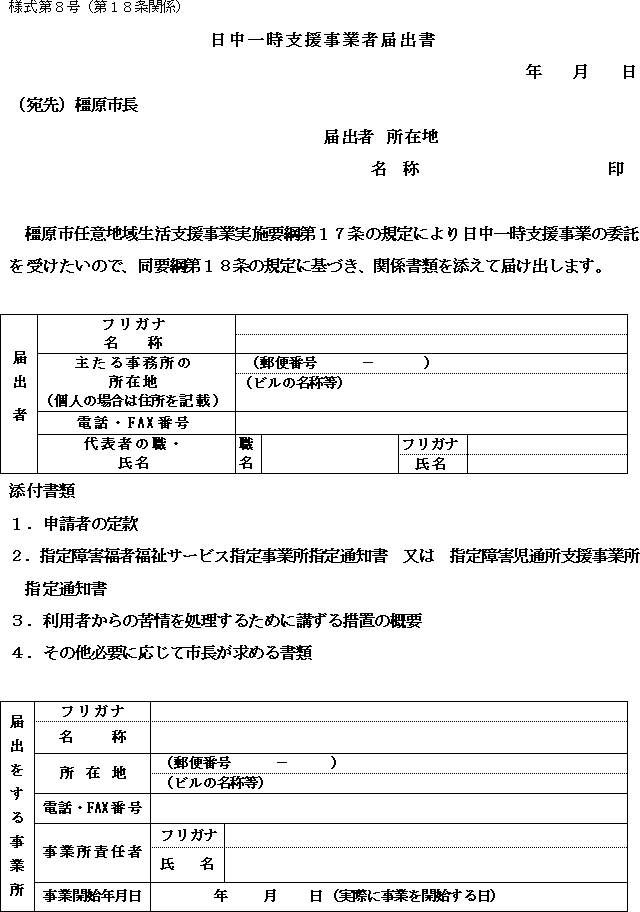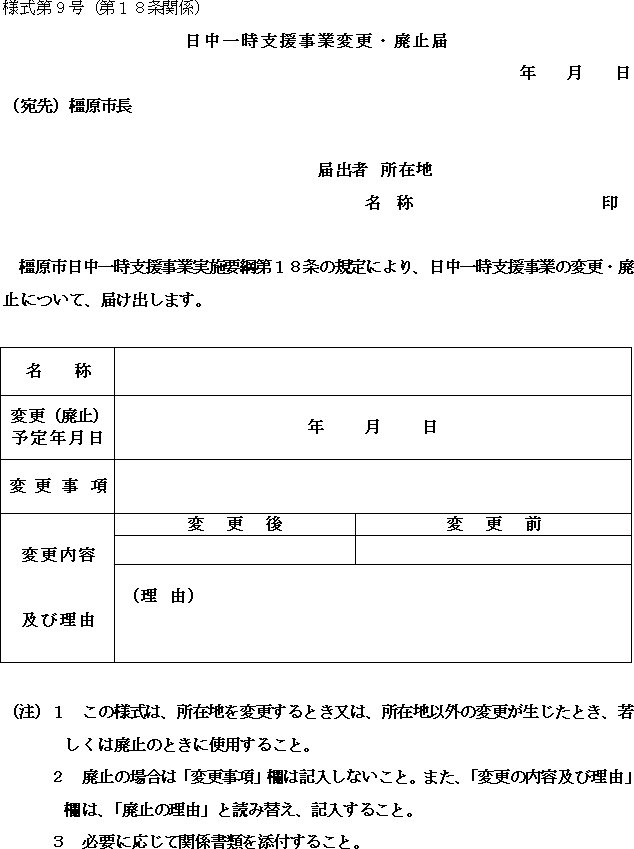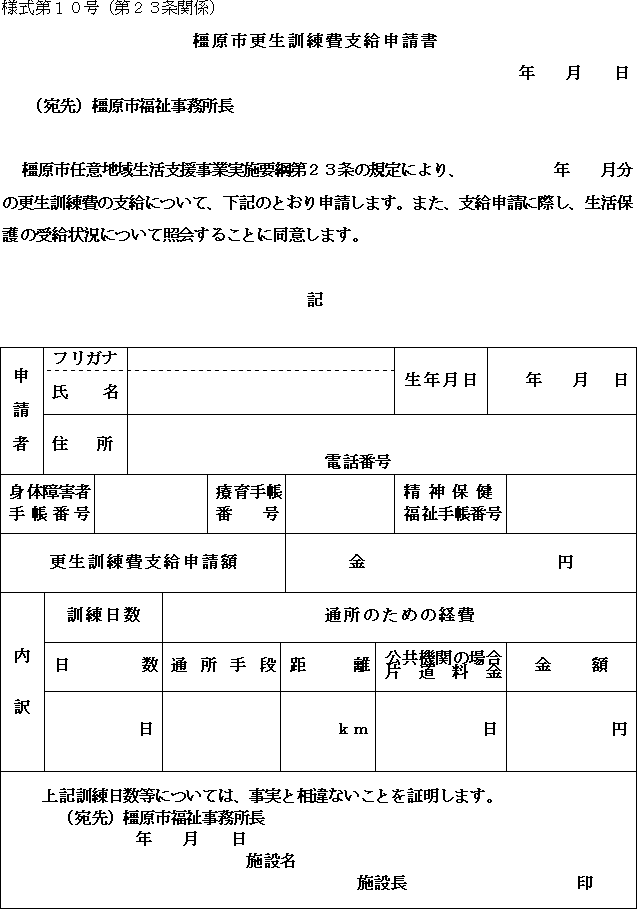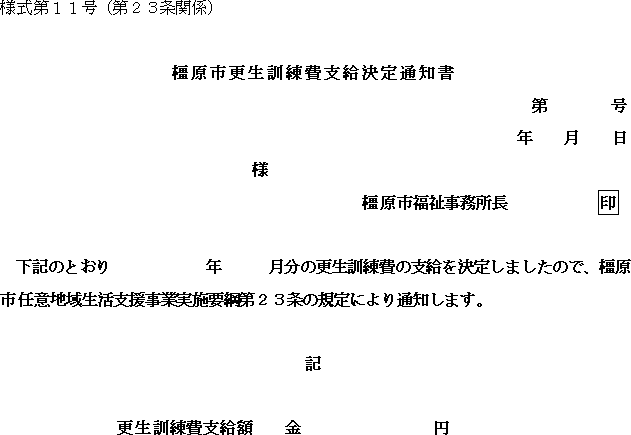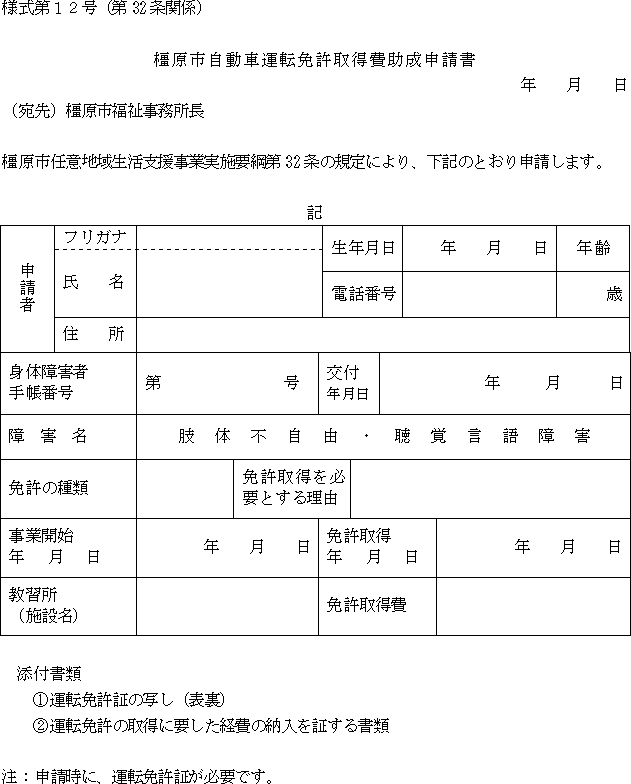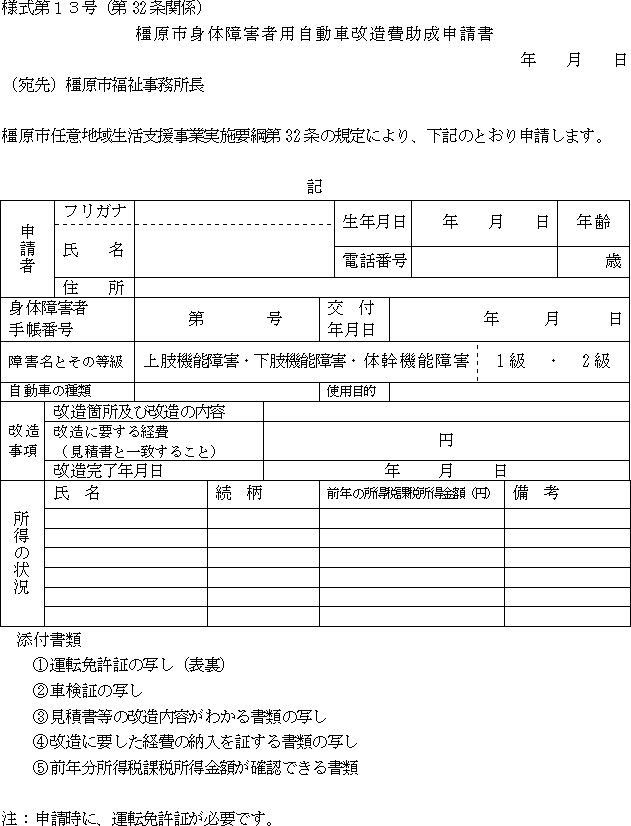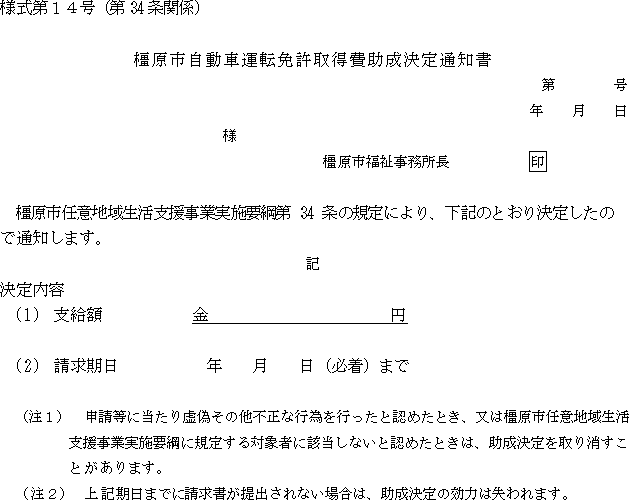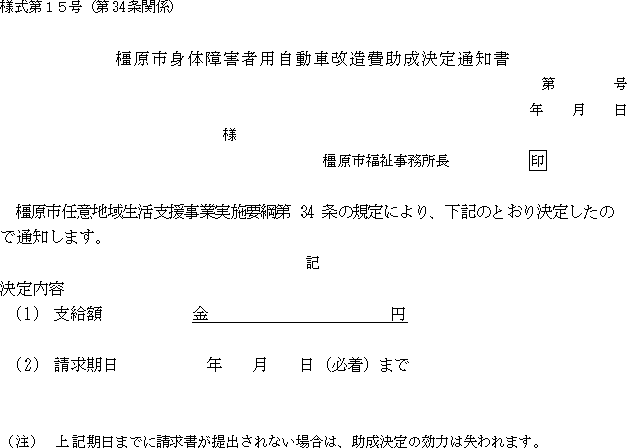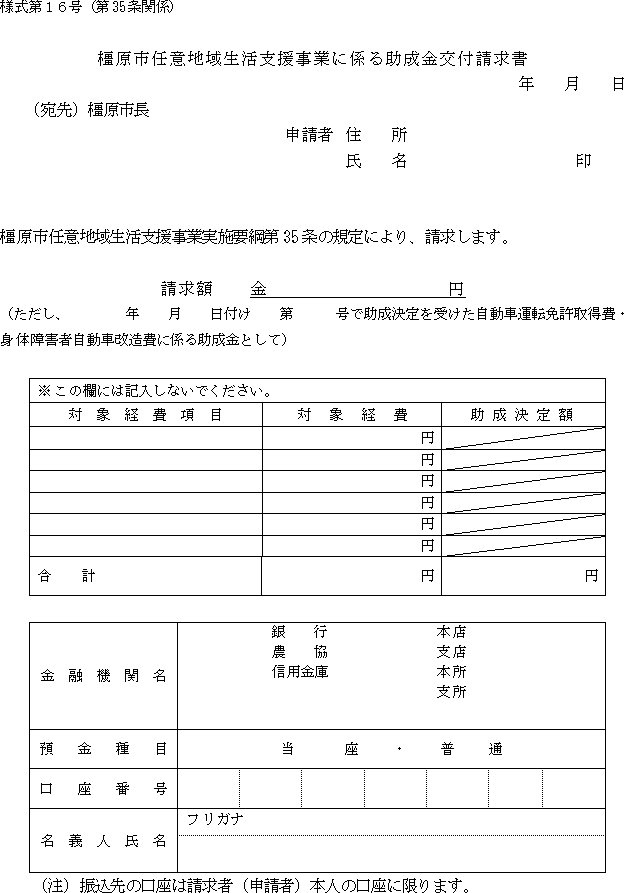○橿原市任意地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第194号
橿原市任意地域生活支援事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給付事業
第1節 訪問入浴サービス事業(第3条~第10条)
第2節 日中一時支援事業(第11条~第20条)
第3節 更生訓練費給付事業(第21条~第25条)
第3章 助成事業
第1節 自動車運転免許取得費助成事業(第26条~第28条)
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第29条~第31条)
第3節 助成手続等(第32条~第37条)
第4章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による任意地域生活支援事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、18歳未満のものをいう。
(3) 知的障害者 奈良県の療育手帳(次号において「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち、18歳以上のものをいう。
(4) 知的障害児 療育手帳の交付を受けている者のうち、18歳未満のものをいう。
(5) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(次号において「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち、18歳以上のものをいう。
(6) 精神障害児 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、18歳未満のものをいう。
(7) 難病患者 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者(次号において「難病患者等」という。)のうち18歳以上であるものをいう。
(8) 難病児童 難病患者等のうち18歳未満の者をいう。
(9) 障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者(第13条及び別表1(備考を含む。以下この号において同じ。)において「障害者」という。)並びに身体障害児、知的障害児、精神障害児及び難病児童(第13条及び別表1において「障害児」という。)をいう。
(10) 任意地域生活支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定により行う次に掲げる事業をいう。
ア 訪問入浴サービス事業
イ 日中一時支援事業
ウ 更生訓練費給付事業
エ 自動車運転免許取得費助成事業
オ 身体障害者用自動車改造費助成事業
(11) 給付事業 任意地域生活支援事業のうち訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業及び更生訓練費給付事業をいう。
(12) 助成事業 任意地域生活支援事業のうち自動車運転免許取得費助成事業及び身体障害者用自動車改造費助成事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
第2章 給付事業
第1節 訪問入浴サービス事業
(事業内容)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下この節において「事業」という。)とは、訪問により居宅において入浴サービスを提供することをいう。
2 事業は、移動式の入浴セットを居宅に搬送し、入浴介助者の援助によって行うものとする。
3 事業の利用回数は、対象者1人当たり原則として1週間に1回とし、1月に5回までとする。ただし、福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住する身体障害者若しくは身体障害児又は難病患者若しくは難病児童で、寝たきり等の理由により居宅において家族等の介護を得ても入浴が困難であると所長が認める者
(2) 健康上及び公衆衛生上入浴に支障がない者
(3) 医師が入浴可能と認めた者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問入浴介護の対象とならない者
(利用の手続)
第5条 事業を利用しようとする者(その者を扶養する者を含む。以下この節において「申請者」という。)は、毎年度、橿原市訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)、医師の証明書及び訪問入浴サービス利用誓約書を、所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定により提出された申請書及び添付書類の内容を審査し、事業の利用を認める場合は、橿原市訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、その利用を認めない場合は、橿原市任意地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により事業の利用を認められた者(以下この節において「利用者」という。)は、事業の利用に当たっての事故等を防止するため、事前に主治医等の意見を聴き、必要に応じて診断を受けるよう努めるものとする。
(費用負担)
第6条 利用者は、事業の利用に当たっては、利用1回につき12,500円(以下この節において「費用負担額」という。)を負担するものとする。
2 市は、利用者が事業を利用したときは、当該費用負担額の100分の95に相当する額を当該利用者に給付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者が事業を利用した場合にあっては、100分の100に相当する額を当該利用者に給付するものとする。
3 市は、利用者が給付事業を利用したときは、前項の規定により給付すべき額を、当該利用者に代わり、第8条の規定により当該給付事業を委託した事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対して第2項の規定による給付があったものとみなす。
(利用の廃止)
第7条 利用者は、第5条の規定により申請した内容に変更が生じたとき、又は事業を利用しなくなったときは、橿原市任意地域生活支援事業利用変更・廃止届(様式第4号)により、速やかに、所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の規定による利用の廃止の届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を廃止するものとする。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他所長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。
3 所長は、第1項の規定による変更の届出を認めたとき、又は前項の規定により利用者に対して事業の利用の廃止を決定したときは、橿原市任意地域生活支援事業利用変更・廃止決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
(委託)
第8条 市長は、介護保険法第70条第1項の規定により訪問入浴介護の指定居宅サービス事業者として指定を受けた事業所に対し、当該事業を委託することができる。
(報告)
第9条 訪問入浴サービス事業者は、訪問入浴サービス事業の実施の状況を、定期に所長に報告しなければならない。
(調査等)
第10条 所長は、訪問入浴サービス事業者に対し、訪問入浴サービス事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。
第2節 日中一時支援事業
(事業内容)
第11条 日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)とは、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、日中における障害者等の活動の場を確保することをいう。
2 事業の利用日数は、対象者1人当たり1月に5日までとする。ただし、就学している障害者等が7月又は8月に事業を利用する場合における事業の利用日数は、対象者1人当たり当該各月に7.5日までとする。
3 利用日数の計算については、次の各号に掲げる利用時間の区分に応じて、当該各号に定める利用日数に換算して計算するものとする。
(1) 4時間以下の場合 0.25日
(2) 4時間を超え8時間以下の場合 0.5日
(3) 8時間を超える場合 0.75日
4 第2項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認める場合は、第2項に規定する利用日数を変更することができる。
(併給関係)
第12条 日中一時支援は、日中活動系サービスとみなすため、法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援との同じ場所での連続した利用は原則として認めないものとする。
(対象者)
第13条 事業の対象者は、市内に居住する障害者等とする。ただし、施設入所支援、療養介護又は共同生活援助の支給決定を受けている者若しくは介護保険の被保険者(介護保険法第9条に規定する被保険者をいう。)を除く。
(利用の手続)
第14条 事業を利用しようとする者(その者を扶養する者を含む。以下この節において「申請者」という。)は、橿原市日中一時支援事業利用申請書(様式第6号)を、所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定により提出された申請書及び添付書類の内容を審査し、事業の利用を認める場合は、橿原市日中一時支援事業利用決定通知書(様式第7号)により、その利用を認めない場合は、橿原市任意地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第15条 前条の規定により給付事業の利用を認められたもの(以下この節において「利用者」という。)は、給付事業の利用に当たっては、別表1に定める費用負担額(以下この節において「費用負担額」という。)を負担するものとする。
2 市は、利用者が事業を利用したときは、当該費用負担額の100分の95に相当する額を当該利用者に給付するものとする。ただし、生活保護法による被保護者又は市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。)非課税世帯に属する者が事業を利用した場合においては、別表2に定める額を給付する。この場合において、障害支援区分の認定を受けていない障害児が18歳に到達した場合、当該到達した年度の末までの間は、当該障害児については、障害児の世帯範囲を適用する。
3 市は、利用者が給付事業を利用したときは、前項の規定により給付すべき額を、当該利用者に代わり、第17条の規定により当該給付事業を委託した事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対して第2項の規定による給付があったものとみなす。
(利用の廃止)
第16条 利用者は、第13条の規定により申請した内容に変更が生じたとき、又は事業を利用しなくなったときは、橿原市任意地域生活支援事業利用変更・廃止届(様式第4号)により、速やかに、所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の規定による利用の廃止の届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を廃止するものとする。
(1) 第13条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他所長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。
3 所長は、第1項の規定による変更の届出を認めたとき、又は前項の規定により利用者に対して給付事業の利用の廃止を決定したときは、橿原市任意地域生活支援事業利用変更・廃止決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
(委託)
第17条 市長は、法第36条第1項の規定により日中活動系サービス又は短期入所の指定障害福祉サービス事業者として指定を受けた事業所又は児童福祉法第21条の5の15の規定により児童発達支援若しくは放課後等デイサービスの指定障害児通所支援事業者として指定を受けた事業所に対し、当該事業を委託することができる。
(受託の手続)
第18条 前条の規定による任意地域生活支援事業の委託を受けようとする者(以下「届出者」という。)は、日中一時支援事業者届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出者が日中一時支援事業を実施する能力を有するか否かを審査し、有すると認めたときは、当該届出者と日中一時支援事業の委託に関する契約を締結するものとする。
3 前項の契約の期間は、当該契約を締結した日から当該年度末までとする。
4 第2項の契約を締結し、日中一時支援事業を受託した者(以下「日中一時支援事業者」という。)は、第1項の届出書(次項の規定により省略する場合は、当該事業者が前年度以前に提出したもの)に記載している事項に変更が生じたとき、又は受託していた日中一時支援事業を廃止しようとするときは、日中一時支援事業変更・廃止届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。
5 市長は、前年度に日中一時支援事業者であった者が引き続き日中一時支援事業の委託を受けようとする場合は、第1項による届出書の提出を省略させて、第2項の契約を締結することができる。
(報告)
第19条 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業の実施の状況を、定期に所長に報告しなければならない。
(調査等)
第20条 所長は、日中一時支援事業者に対し、日中一時支援事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。
第3節 更生訓練費給付事業
(事業内容)
第21条 更生訓練費給付事業(以下この節において「事業」という。)とは、自立訓練(法第5条第12項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)又は就労移行支援(法第5条第13項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)に係る事業を利用している者の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費を支給することをいう。
(対象者)
第22条 事業の対象者は、法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた身体障害者のうち、生活保護法の規定による保護を受けている者であり、かつ、自立訓練又は就労移行支援に係る事業を利用している者とする。
(利用の手続)
第23条 事業を利用しようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、橿原市更生訓練費支給申請書(様式第10号)を、所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定により提出された申請書及び添付書類の内容を審査し、事業の利用を認める場合は、橿原市更生訓練費支給決定通知書(様式第11号)により、その利用を認めない場合は、橿原市任意地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(給付)
第24条 前条の規定により給付事業の利用を認められた者(以下この節において「利用者」という。)に対しては、次に掲げる通所のための経費を給付するものとする。ただし、自動車等を利用して通所する者については、その訓練日数が15日以上あった月に限る。
(1) 公共交通機関等利用者については、日額300円に更生訓練のために当該月に通所した日数を乗じて得た額と当該月の公共交通機関等の利用に係る実支出額とを比較して少ない方の額
(2) 通所距離が2キロメートル以上5キロメートル未満の自動車等利用者については、月額2,000円
(3) 通所距離が5キロメートル以上の自動車等利用者については、月額4,100円
2 市は、利用者が給付事業を利用したときは、前項の規定により給付すべき額を、当該利用者に代わり、利用者の利用する事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対して第1項の規定による給付があったものとみなす。
(利用の廃止)
第25条 利用者は、第22条の規定により申請した内容に変更が生じたとき、又は事業を利用しなくなったときは、橿原市任意地域生活支援事業利用変更・廃止届(様式第4号)により、速やかに、所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の規定による利用の廃止の届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を廃止するものとする。
(1) 第22条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他所長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。
3 所長は、第1項の規定による変更の届出を認めたとき、又は前項の規定により利用者に対して給付事業の利用の廃止を決定したときは、橿原市任意地域生活支援事業利用変更・廃止決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
第3章 助成事業
第1節 自動車運転免許取得費助成事業
(事業内容)
第26条 自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)とは、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し、その取得に要した費用の一部を助成することをいう。
(対象者)
第27条 事業の対象者は、市内に住所を有する自動車運転免許証の交付を受けた身体障害者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 肢体不自由である者又は聴覚言語障害を有する者
(2) 肢体不自由又は聴覚言語障害のため、自動車運転免許に条件が付される者
(助成の金額)
第28条 助成する金額は、自動車運転免許の取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)に、次の各号に掲げる身体障害者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた額とする。ただし、肢体不自由者にあっては100,000円を、聴覚言語障害者にあっては50,000円を限度とする。
(1) 肢体不自由者 3分の2
(2) 聴覚言語障害者 3分の1
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業
(事業内容)
第29条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下この節において「事業」という。)とは、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「就労等」という。)に伴い、自らが所有し、運転する自動車を改造した場合に、その改造に要した経費を助成することをいう。
(対象者)
第30条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の程度が1級又は2級に該当する身体障害者
(2) 自動車運転免許証を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があると所長が認める者
(4) 本人及びその配偶者について、改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の金額)が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成の金額)
第31条 助成する金額は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費のうち所長が認める額とし、100,000円を限度とする。
第3節 助成手続等
(助成の申請)
第32条 助成事業による助成金(以下この節において「助成金」という。)の交付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に定める申請書及び添付書類を、所長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得費助成事業 橿原市自動車運転免許取得費助成申請書(様式第12号)並びに取得した自動車運転免許証の写し及びその取得に要した経費の納入を証する書類
(2) 身体障害者用自動車改造費助成事業 橿原市身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第13号)、改造を行った内容及びその経費の納入を証する書類その他所長が必要と認める書類
(申請の期限)
第33条 前条の規定による申請は、自動車運転免許取得費助成事業にあっては自動車運転免許証の交付を受けた日から、身体障害者用自動車改造費助成事業にあっては改造を完了した日から6月以内に行わなければならない。
(助成の決定)
第34条 所長は、第32条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容を審査し、助成金の交付を認める場合は、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に定める助成決定通知書により、その利用を認めない場合は、橿原市任意地域生活支援事業利用却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 自動車運転免許取得費助成事業 橿原市自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第14号)
(2) 身体障害者用自動車改造費助成事業 橿原市身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第15号)
(交付の請求)
第35条 前条の規定により助成金の交付を認められた者(以下この節において「助成決定者」という。)は、速やかに、橿原市任意地域生活支援事業に係る助成金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第36条 市長は、前条の規定により助成決定者から助成金の請求を受けたときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第37条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた助成決定者に対し、既に交付した助成金の返還を命じることができる。
第4章 雑則
(その他)
第38条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年10月1日から実施する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 橿原市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成11年橿原市告示第61号)
(2) 橿原市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成12年橿原市告示第179号)
(3) 橿原市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成12年橿原市告示第180号)
附 則(平成19年3月15日告示第46号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日告示第65号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日告示第86号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施前にこの要綱による改正前の橿原市任意地域生活支援事業実施要綱の規定により任意地域生活支援事業の委託を受けている団体等については、当分の間、改正後の橿原市任意地域生活支援事業実施要綱の規定に定める事業所とみなし、任意地域生活支援事業を委託することができるものとする。
附 則(平成25年4月1日告示第118号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成27年1月20日告示第16号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度の任意地域生活支援事業から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年11月29日告示第313号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日告示第163号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年12月28日告示第356号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
別表1(第15条関係)
日中一時支援事業の利用に係る費用負担額
障害支援区分 | 利用時間 | |||
4時間以下の場合 | 4時間を超え8時間以下の場合 | 8時間を超える場合 | ||
障害者 | 区分6 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
区分5 | 2,100円 | 4,200円 | 6,300円 | |
区分4 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | |
区分3 | 1,600円 | 3,200円 | 4,800円 | |
区分2 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | |
区分1 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | |
障害児 | 区分3 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
区分2 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | |
区分1 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | |
食事提供加算 | 420円 | |||
送迎加算 | 540円 | |||
備考
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分の認定を受けていない障害者については、障害支援区分の区分1を適用する。障害児については、障害児の調査票による区分を適用する。ただし、当該区分の1から3のいずれにも該当しない場合は、区分1の料金を適用する。また、障害支援区分の認定を受けていない障害児が18歳に到達した場合、当該到達した年度の末までの間は、当該者については、障害児の料金区分を適用する。
2 「食事提供加算」とは、第15条第2項の規定により市が100分の100に相当する額を給付する者に対して、障害者の日常生活及び生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年告示523号)別表第6の10に規定する方法による加算をいう。
3 「送迎加算」とは、利用者を事業所の車によって送迎を行った場合に行う加算をいう。
別表2(第15条関係)
利用世帯の所得階層区分 | 市の負担割合 | |
障害児 | 市町村民税課税世帯であるとき | 100分の95 |
市町村民税非課税世帯であるとき | 100分の100 | |
障害者 | 当該障害者の市町村民税が課税であるとき(当該障害者に配偶者がいる場合は、利用者及び配偶者のうちどちらかまたは両方が課税であるとき。) | 100分の95 |
当該障害者(当該障害者に配偶者がいる場合は、配偶者を含む。)の市町村民税が非課税であるとき | 100分の100 | |
生活保護法による被保護者 | 100分の100 | |
備考
1 「世帯」とは、利用者及び住民票上における同一世帯員をいう。
2 「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、住民票上における同一世帯員と認められたすべての者が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「被保護者」とは、生活保護法による生活扶助・医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている者をいう。
5 障害支援区分の認定を受けていない障害児が18歳に到達した場合、当該到達した年度の末までの間は、当該者については、障害児の世帯範囲を適用する。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、別に定める様式を市長に提出し、市長が認めた場合に限り、それぞれ当該各号に定める者とみなし、市町村民税の額を算定する。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻または事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものをいう。以下この項において同じ。)をしていない者のうち、扶養親族又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者に限る。以下この項において同じ。)を有するもの 地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻または事実婚をしていない者のうち、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下であるもの 地方税法第292条第1項第12号に規定する寡夫