坪井・大福遺跡
(つぼい・だいふくいせき)
坪井・大福(つぼい・だいふく)遺跡は橿原市の北東部に位置し、都市化の波が押し寄せてはいるものの、のどかな田園風景が多く残る地域で、奈良盆地東南部、多武峰(とうのみね)の北東から北西に流れる寺川の右岸に立地する標高約65メートルの水田地帯です。周辺には寺川水系に沿って大福池(だいふくいけ)、東新堂(ひがししんどう)遺跡など縄文時代晩期から弥生時代にかけての遺跡群が分布しています。もともとは橿原市北東部に位置する坪井遺跡と、桜井市北西部に位置する大福遺跡の、それぞれ単独の遺跡と考えられていました。かねてから大和における弥生時代の主要遺跡の一つとして考えられてきましたが、本格的な調査は1986・87年(昭和56・57年)に奈良県立橿原考古学研究所によって耳成高校建設のための事前調査が実施され、これを契機に橿原市教育委員会が数次にわたり調査を実施しました。その結果、環濠と思われる大溝や土坑、井戸、墓地群などの遺構が確認されています。とくに、1987年(昭和62年)に行われた第7次調査においても類例が少ない弥生時代前期末の木棺墓が2基検出され、棺内には良好な状態で人骨が残っていました。また、土器、石器、木製品、獣骨類なども遺物も大量に出土しています。なかでも土器片に人物などが描かれた線刻画土器、有柄式銅剣(ゆうへいしきどうけん)を模してつくられた木製の柄頭(つかがしら)など全国的にも類例を見ない遺物も含まれています。このことから坪井遺跡と大福遺跡は弥生時代前期から古墳時代まで継続する一つの大集落跡であることがわかりました。遺構の密度、遺物量などから唐古・鍵遺跡(田原本町)と同様に大和を代表する弥生時代の遺跡です。

環濠

土器棺検出状況

前期土器

中期土器

後期土器
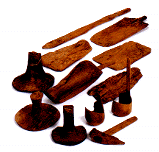
木製品類
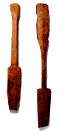
木製品(鋤)

石製品

石包丁
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
文化財保存活用課
奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)
電話:0744-47-1315
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



































更新日:2023年03月28日