くらしの情報(地球環境編)
1)循環型社会【じゅんかんがたしゃかい】
地球と共生し、持続可能な社会を実現するためには、社会のあらゆる主体が環境を考慮し、社会システムのあり方を転換していく必要があります。21世紀の進むべき道として考えられたのが「環境型社会」です。
わが国では、持続可能な社会を目指し、「循環型社」をつくるための基本的な法律「環境型社会形成推進基本法(循環型社会基本法)」が制定し、2001年より施行されています。
循環型社会基本法では、循環型社会とは、1.製品等が廃棄物等になることを抑制、2.排出された廃棄物等はできるだけ資源として利用し、3.最後にどうしても利用できないものは適正に処分することを徹底することが、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」であると規定しています。
2)循環型社会を支える”3R”【スリーアール】から”5R”へ!
環境と経済が両立した循環型社会を支える考え方・取り組みを「3R」と呼ばれています。循環型社会基本法において導入された「3R」とは、
- Reduce(リデュース)…ごみの発生抑制
- Reuse(リユース)…ごみの再使用
- Recycle(リサイクル)…ごみの再生利用、資源としての利用
- 「3R」とは、上記の頭文字をとった言葉です。
- 「3R」は環境負荷をできる限り低減するという観点から、優先順位が1.~3.と決められています。
- 「3R」の意味は、下段に説明しています。また、最近では、新たに、4.Refuse(リフューズ:断る)、5.Repair(リペア:修理)を加えて、「5R」が登場しています。
3)Reduce【リデュース】…発生抑制
でてくるごみをできるだけ減らすことです。
4)Reuse【リユース】…再利用
不用になったものを、できるだけくり返し使うことです。
5)Recycle【リサイクル】…再生利用、再資源化
くり返し使えないものは、資源としてリサイクルすることです。
6)ISO14001【アイエスオー14001】
国際標準化機構(ISO:InternationalOrganizationforStandardization)、による環境マネジメントシステムの国際規格(環境を守るための国際規格)のこと。
事業所内に環境マネジメントシステム(EMS:EnvironmentalManagementSystem)をつくり、環境対策を行うために環境方針や計画(Plan)の策定・実施(Do)・結果の点検(Check)・見直し(Action)を行い、継続的な改善を図っていく仕組みです。
事業活動から排出される廃棄物についても、環境マネジメントシステムの中に組み込んでいくことにより、計画的に減量化を進めることができます。
7)環境負荷を測る指標-LCA(LifeCycleAsessment:ライフ・サイクル・アセスメント)
ある製品に対して、原料の調達から製造、流通、消費、廃棄などすべての段階を通して環境に与える影響を数値化して総合評価する方法です。数値は、各段階で使用される資源・エネルギーの投入量、廃棄物、温室効果ガスや汚染物質などが使われています。
環境負荷は、ある段階だけを見て省エネであるかを判断するのではなく、「モノの一生」を通して評価する必要があります。LCA手法で食品の生産から消費・廃棄物処理までの一連の燃料エネルギーの総量を分析すると、米(6,330カロリー/キログラム)、パン類(9,510カロリー/キログラム)、めん類(15,040カロリー/キログラム)です。
8)製品のCO2の「見える化」:カーボンフットプリント(CFP【CarbonFootopintofProducts:炭素の足跡】)
直訳すると、「炭素の足跡」となります。「カーボンフットプリント」とは、製造から流通、廃棄までのCO2排出量を算定し表示することをいいます。商品・サービスのライフサイクルの各過程で排出された「温室効果ガスの量」を合算した結果、得られた全体の量をCO2量に換算して表示することを言います。
経済産業省が策定した基本ルールでは、商品の購入による環境への影響を消費者に“見える化(可視化)”するため、共通ラベルを用いて表示させることになっています。
尚、ラベルは、商品本体または包装資材に貼るのが原則となっていて、統一マークが定められています。(下記)(注意)詳細は、経済産業省「CFP」のページへ(外部リンク)

算定される温室効果ガスは、京都議定書の対象となっている6つです。
算定される温室効果ガス
- 二酸化炭素(CO2)
- メタン(CH4)
- 酸化二窒素/亜酸化窒素(N2O)
- ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)
- パーフルオロカーボン類(PFCs)
- 六フッ化硫黄(SF6)
9)カーボンオフセット(CarbonOffset)
カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。イギリスを始めとした欧州、米国、欧州等での取組が活発であり、我が国でも民間での取組が拡がりつつあります。
身近なところでは、「カーボンオフセットはがき」でおなじみです。
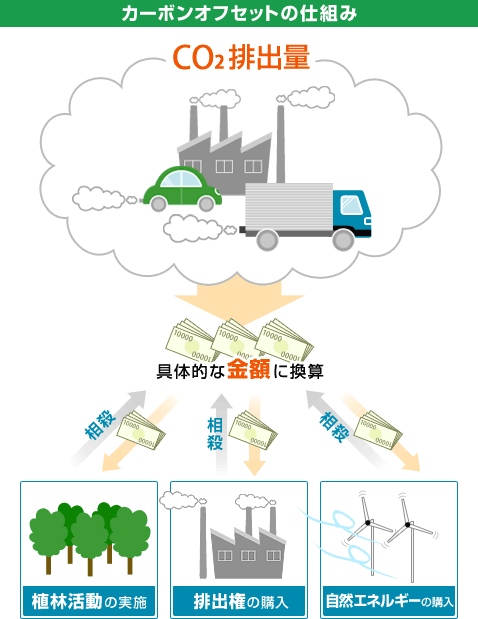
10)識別マーク【しきべつマーク】
容器包装のリサイクルをすすめるためにには「識別マーク」を表示することになっています。識別マークにより、住んでいる地域の分別ルールに従したがって排出しましょう。
ごみを資源としてよみがえらせるには、正しい分別が必要です。
11)グリーンコンシューマー
環境負荷の大きい商品には環境税などを課し、需要を抑制する方法として、北欧諸国では、炭素税が導入されています。私たちの生活基盤である「家計」は、環境にやさしい経済行動をし、持続可能な経済社会を構築する責任を負っているといえます。そうした責任を自覚して消費活動をすること(人)を「グリーンコンシューマー」といいます。
12)マイバックで省エネ!
買い物の際、マイバック(買い物袋)を持参することで、最終的にごみとなるレジ袋の使用を少なくし、そうした行動を通じて、住民のごみ減量化行動の意識を高めていくものです。
ちなみに、国内で使われているレジ袋は、年間305億枚(LLサイズ)とも言われています。
13)パッシブシステム
パッシブシステムとは、建築を取り巻く自然エネルギー(太陽、風、空気、熱など)を機械や装置を使わずそのまま活かし、少ないエネルギーで住宅の内部環境を良くしようとするシステムのことをいいます。雨水をトイレや庭の散水などに利用する「雨水利用システム」、壁面や屋上などに植物を植えて建物の温度上昇を防ぐ、「屋上緑化・緑のカーテン」、深い軒やひさし、南面の大きな開口部などで暑さをやわらげたり暖をとる「パッシブソーラーシステム」、風の流れを考慮した「通風計画」など、建物の設計によって集熱、蓄熱、断熱などの性能を高める住まいを創造するシステムをいいます。
橿原市役所の庁舎にもグリーンカーテンが設置され、強い日差しによる庁舎内の温度上昇を抑制しています。

橿原市役所の中庭にゴーヤ、へちま、朝顔等が植栽されています。
14)アクティブシステム
アクティブシステムとは、太陽の熱や光(ソーラー)、風などの自然エネルギーを機械・装置を使って利用することです。代表的なものとしては、「太陽熱温水器」、「太陽光発電」や「風力発電」があげられます。
15)リターナブル容器【リターナブルようき】
洗浄・消毒等を行ったのちに再度、同じ用途で再利用される容器のことで、ビールびんや牛乳びんなどがリターナブルびんとして利用されています。
16)ワンウェイびん
そのままの形では使用できず、一度くだいてカレットにし、高温で溶かして再びガラスびんとして利用されます。
17)食材の距離と省エネ―フードマイレージ(FoodMileage)と地消地産
食料の生産地から食卓までの距離に注目し、なるべく近くでできたものを食べようという考え方です。食料に運送に伴う環境負荷の大きさを測る指標として考え出された概念で、イギリスの消費者運動家であるティム・ラングが提唱したことがきっかけとなりました。
食料輸入量×運送距離(単位:トン・キロメートル)で示され、数値が小さいほど輸送のためのエネルギー消費が少なく環境負荷も減少します。外国産の食材を食べるより地元や国産の食材を食べるだけで、エアコンの温度を1℃下げるぐらいのC02を減らすことができると言われています。
(注意)日本のフードマイレージ:9,002億トン・キロメートル(米国や韓国の約3倍)
ちなみに、距離だけでなく、季節を考えて食材を選ぶことも省エネとなります。近年では、一年中をとおしてさまざまな食材が市場に出回っていますが、旬の食材を選ぶことにより、ハウス栽培などで消費するエネルギーの節約にも貢献できますね。
18)マテリアルリサイクル
廃棄物を原料、材料などのものとして再利用することです。
19)サーマルリサイクル
廃棄物を焼却して、その熱エネルギーを発電やプールや温泉の熱源に再利用することです。
20)ペットtoペット
ペットボトルをペットボトル樹脂に再生して、ペットボトルを作ることです。
21)バーチャルウォーター
バーチャルウォーターとは、輸入物資を仮に自国で生産した場合に使われるであろう水のことです。とうもろこし1キログラムを作るには、1.9トン、牛肉の場合は、20.7トンもの水が必要と言われています。
22)省エネラベリング制度
2000年に導入された「省エネラベリング制度(省エネラベル)は、家電製品等が省エネ法で定められた目標基準(トップランナー基準)を達成しているかどうかをラベルに示すもので、JIS法で規定されています。2008年時点で、トップランナー基準の特定機器のうち、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、蛍光灯、パソコンなど、16製品が対象になりました。省エネラベルは、省エネ性マーク、省エネ基準達成率、エネルギー消費効率、目標年度の4つの情報を表示し、トップランナー基準に達していれば、緑色のマーク、未達成の場合は、だいだい色のマークが表示されています。また、エアコン、電気冷蔵庫、テレビの3製品については、2006年の改正省エネ法により、多段階評価を導入し、「統一省エネラベル」として、製品の性能を5段階の星印で評価されることになりました。

統一省エネラベル

23)エコクッキング
エコクッキングとは、総じて、環境にやさしい、ゴミが少ない料理方法です。
内容には
- 買い物方法
- 保管方法
- 調理方法
- 食事方法
- 捨て方があります。
買い物や調理の仕方にも様々な工夫が必要です。最近は、古紙やペットボトルなどの家庭のゴミ・資源の資源化の技術革新が進んでいますが、まずは生ゴミをなるべく出さないようにすることも大切です。食品の生ゴミは、買い過ぎや食べ残し、賞味期限切れをなるべくなくすことによって減らすことが可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



































更新日:2023年03月28日