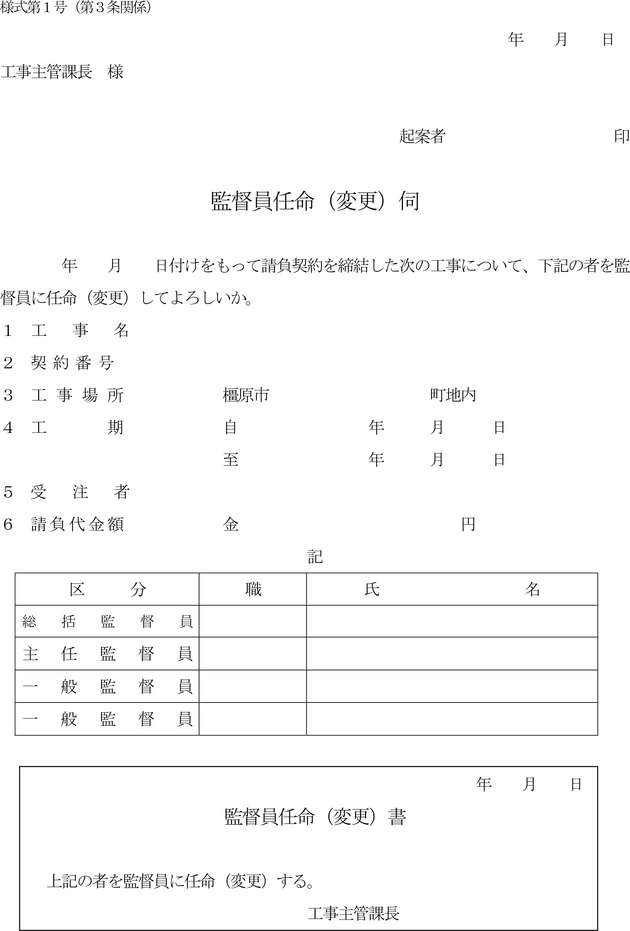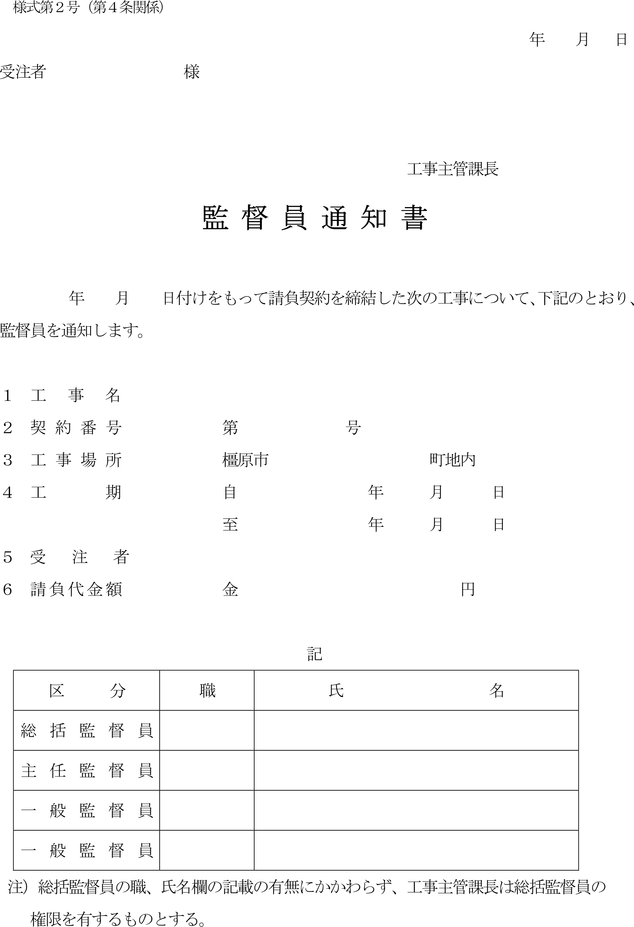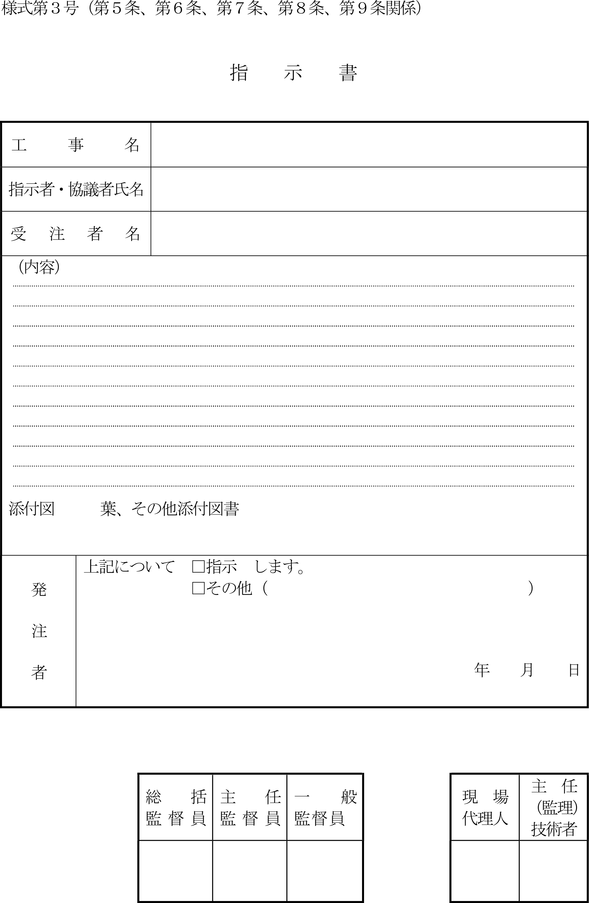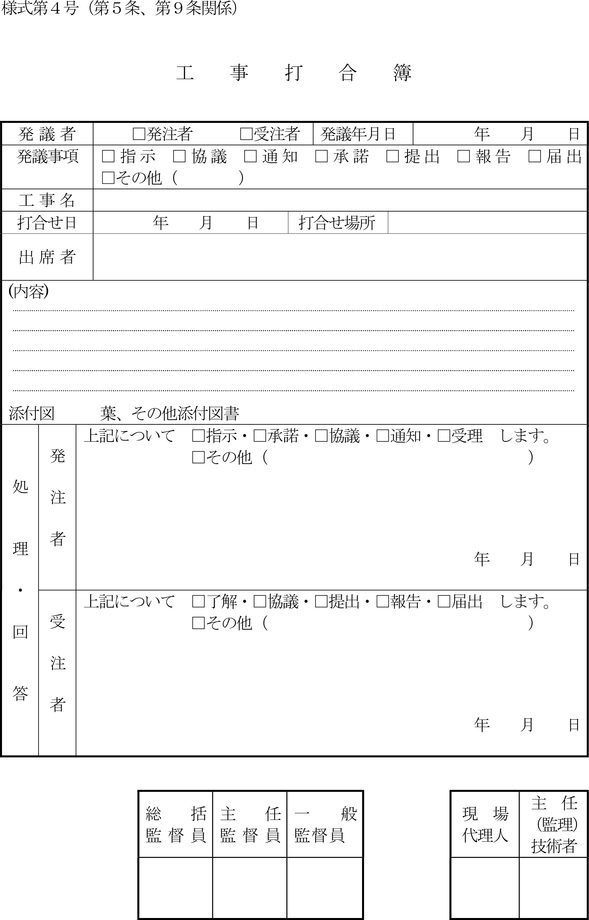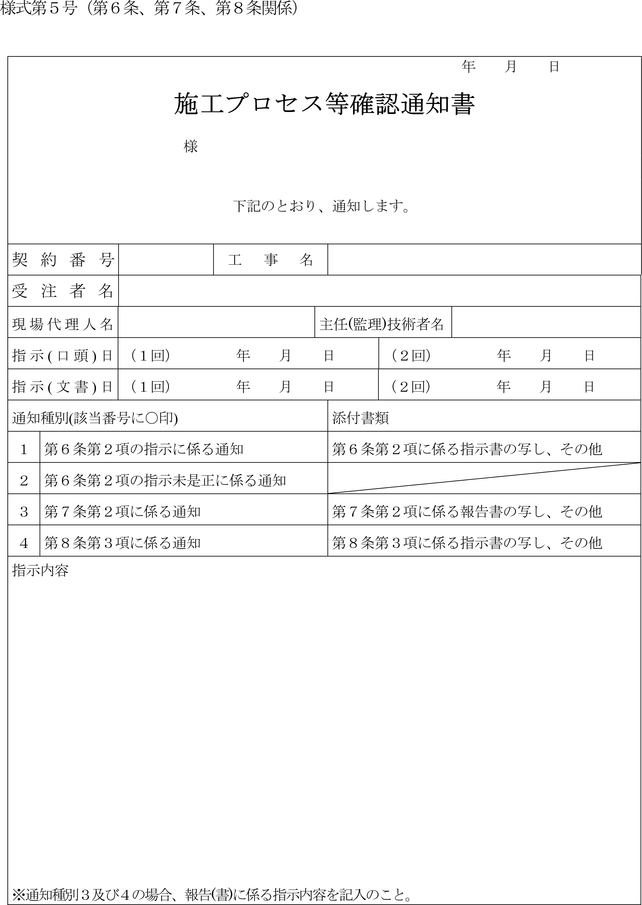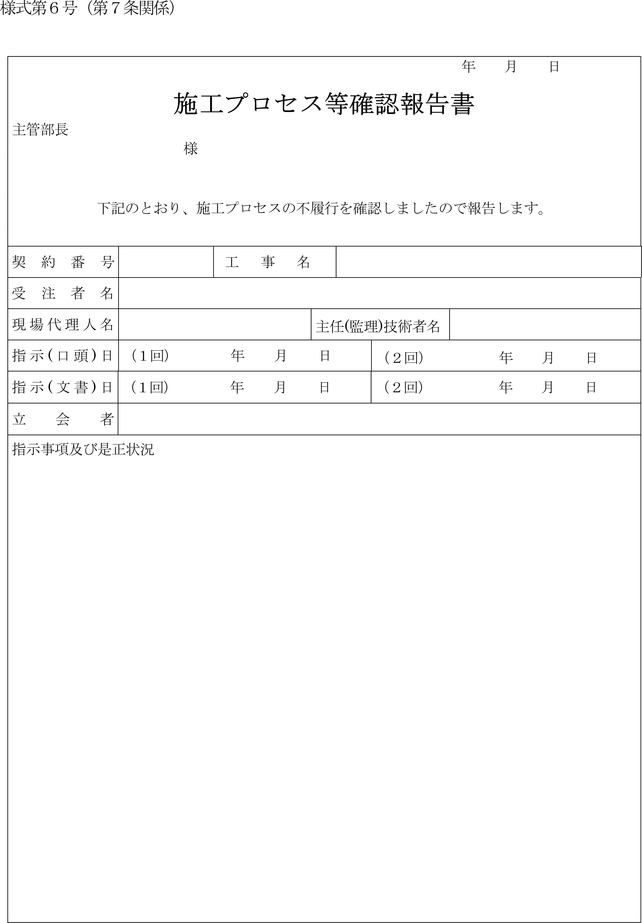○橿原市建設工事監督規程
平成14年1月28日訓令甲第2号
橿原市建設工事監督規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15の規定に基づく建設工事の監督の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事主管課長 建設工事の施工を主管する課等(以下「工事主管課」という。)の長で、監督員を指揮するものをいう。
(3) 監督員 建設工事の監督を行うため、工事主管課長により任命された総括監督員、主任監督員及び一般監督員を総称していう。
(4) 上席の監督員 監督員のうち、一般監督員にあっては主任監督員及び総括監督員をいい、主任監督員にあっては総括監督員をいう。
(5) 検査員 建設工事の検査を行うため、橿原市建設工事検査規程(平成14年橿原市訓令甲第1号)第3条の規定により任命され、同規程第4条第1項の建設工事検査員証の交付を受けた者をいう。
(6) 受注者 橿原市契約規則(昭和39年橿原市規則第7号)の規定に基づき、市と建設工事の請負契約を締結した者をいう。
(7) 設計図書 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(監督員の任命)
第3条 工事主管課長は、建設工事の内容、規模、態様等を考慮し、当該建設工事の契約ごとに別表の区分に応じ、当該各項に定める職員のうちから監督員任命(変更)伺(様式第1号)により任命するものとする。既に任命した監督員を変更するときも同様とする。
2 前項の規定により任命された監督員は、工事目的物の全部の引渡しが完了したときに、特別の手続を要することなく、その職を解かれたものとみなす。
(監督員の通知)
第4条 工事主管課長は、前条第1項の規定により監督員を任命したときは、その氏名等を、監督員通知書(様式第2号)により受注者に通知するものとする。
2 工事主管課長は2人以上の監督員を任命し、次条第2項の権限を分担させる場合は、各々の監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。ただし、同項に定める軽重の判断による分担については、この限りではない。
(監督業務及び分担)
第5条 監督員は、建設工事の履行について、契約書及び設計図書に定める範囲内において監督業務を行う。
2 監督業務は、総括監督員並びに主任監督員が重要なものを、一般監督員が軽易なものを担任するものとし、監督員は、特に工事主管課長が指示したもののほか、概ね次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 工程等の調整処理
(2) 受注者から提出された建設工事関係書類の審査
(3) 契約の履行についての受注者、現場代理人、監理技術者及び主任技術者等(以下「受注者等」という。)に対する指示、承諾、協議、通知若しくは受理(以下「指示等」という。)
(4) 図面及び仕様書に基づく施工のための詳細図等(以下「詳細図等」という。)の作成及び交付又は受注者等が作成した詳細図等の審査及び承諾
(5) 建設工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の工事主管課長への報告
(6) 施工立会並びに工程の管理、建設工事の施工状況の巡視及び検査、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の試験若しくは検査(確認を含む。)
(7) 段階確認(主要な工事段階の区切り検査)、出来形確認(検査員の出来形検査に先立つ検査)、完成確認(検査員の竣工検査に先立つ検査)
(8) 損害発生時の安全措置及び調査並びに災害の防止等のための臨機の措置
3 監督員は、前項3号で規定する指示等については、その軽重を問わず、原則として、指示書(様式第3号)又は工事打合簿(様式第4号)により行い、その交付に際しては、当該監督員の上席の監督員の承認を得るものとする。この場合において、上席の監督員が工事主管課長の承認を必要と認める場合は、工事主管課長の承認を得なければならない。
4 監督員は、前項の指示書又は工事打合簿を交付したときは、その都度、工事主管課長に報告するものとする。ただし、前項後段の規定により業務主管課長の承認を得ている場合は、この限りでない。
(施工体制の確認)
第6条 一般監督員は、橿原市建設工事成績評定に関する事務処理規程(平成15年橿原市訓令甲第15号)様式第1号から第3号までに定める施工プロセスのチェックリスト(以下「チェックリスト」という。)により施工体制について確認し、履行されていないものがあるときは、受注者に口頭注意である旨を伝え、必要な措置を取るよう口頭で指示を行うとともに、その内容を上席の監督員に報告しなければならない。
2 一般監督員は、前項の指示を行った日の翌日から起算して3日以内に指示した内容が是正されないときは、その状況を上席の監督員に報告しなければならない。
3 主任監督員は、前項の報告を受けたときは、その内容を工事主管課長及び総括監督員に報告し、受注者に対し、必要な措置を取るよう指示書により指示を行うとともに契約検査課検査技監(以下「検査技監」という。)に施工プロセス等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 主任監督員は、前項の規定による指示を行った日から起算して3日以内に指示した内容が是正されないときは、その状況を工事主管課長及び総括監督員に報告するとともに検査技監に施工プロセス等確認通知書により通知するものとする。
5 監督員は、橿原市建設工事施工体制点検等実施要綱(平成18年橿原市告示第45号)の規定による調査に協力しなければならない。
(建設工事関係者に関する措置請求)
第7条 工事主管課長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、受注者に対し、必要な措置を取るよう指示書により通知するものとする。
2 工事主管課長は、前項の規定による指示を行った日から起算して3日以内に指示した内容が是正されないときは、その状況を施工プロセス等確認報告書(様式第6号)によりその工事を主管する部長(以下「主管部長」という。)及び検査技監に報告し、主管部長の指示を受けるものとする。
(履行報告の確認)
第8条 監督員は、契約書及び設計図書に定めるところにより、建設工事の履行について、受注者に報告させ、その内容を確認しなければならない。
2 一般監督員は、建設工事の施工において、必要な手続が適切に実施されているかをチェックリスト等により確認しなければならない。
3 前2条の規定は、前2項の確認について準用する。ただし、口頭注意の回数は、同一の内容について、2回までとする。
(建設工事関係書類)
第9条 監督員は、次に掲げる書類(受注者から提出された図書を含む。)等を、建設工事の進ちょくに応じて常に整備し、必要に応じて工事主管課長又は上席の監督員に提出しなければならない。
(1) 契約書
(2) 設計図書及び積算設計書
(3) 施工管理記録(工程管理図書、出来形管理図書、品質管理図書、工事写真等)
(4) 工事請負日誌及び材料購入伝票
(5) 第5条第3項の指示書の写し、工事打合簿及びチェックリスト
(6) その他監督員が必要とする関係書類
(建設工事の記録)
第10条 監督員は、建設工事の施工において、必要な手続が適切に施行されているかをチェックリストにより確認し、記録しなければならない。
(工事材料の検査)
第11条 監督員は、受注者等から設計図書において、監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
2 監督員は、受注者等に対し、前項の検査をした結果、不合格となった工事材料については、7日以内に現場から搬出させなければならない。
(立会い及び工事記録の請求等)
第12条 監督員は、設計図書において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料又は監督員の立会いの上施工するものと指定された工事について、受注者から立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
2 監督員は、7日以内に前項の請求に応じることができず、その後の工程に支障を来すときは、受注者等に対し、材料の調合又は建設工事の施工を適切に行ったことを証する見本の採取又は工事写真等の記録を指示し、これを施工させ、後日その内容の適否を確認しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造請求及び破壊検査等)
第13条 監督員は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しない場合は、上席の監督員に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対し改造を請求しなければならない。
2 監督員は、受注者が契約書第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、上席の監督員に報告し、必要な指示を受けて、建設工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、上席の監督員に報告し、必要な指示を受けて、当該理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲で破壊して検査することができる。
4 前3項の場合において、上席の監督員は、必要に応じて工事主管課長に報告し、指示を求めることができる。
(条件変更等)
第14条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実の確認を受注者から請求されたとき、又は自らその事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき(ただし、これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態その他の施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。
2 監督員は、前項の規定により調査を行う場合は、受注者の意見を聴いて調査の結果(調査内容に対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、工事主管課長等に報告しなければならない。
3 監督員は、調査の終了後14日以内に前項の調査結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いてその期日を延長することができる。
(建設工事の中止)
第15条 監督員は、自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、又は建設工事の現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認められる場合は、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、建設工事の中止内容を受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、監督員は必要があると認めるときは、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、建設工事の中止内容を受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
(工期の変更)
第16条 監督員は、契約書に規定する工期に変更を要する場合は、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、受注者と協議を行うものとする。
(受注者の請求による工期の延長)
第17条 監督員は、天候の不良、契約書第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に建設工事を完成することができないと認められる場合に限り、その理由を明示した書面により、受注者からの工期の延期の請求を受け付けることができる。
(監督員の請求による工期の短縮等)
第18条 監督員は、工期を短縮する必要があるときは、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、その理由を明示した書面により、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
(臨機の措置)
第19条 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認める場合は、上席の監督員に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。ただし、緊急又はやむを得ない事情があるときは、その事後において報告できるものとする。
2 監督員は、前項の規定により臨機の措置をとることを請求したときは、工事主管課長に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 監督員は、建設工事の施工について、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに調査を行い、安全措置を受注者に対し命じるとともに、その結果を工事主管課長等に報告しなければならない。この場合において、必要な指示があるときは、受注者に通知しなければならない。
(不可抗力による損害)
第21条 監督員は、工事目的物の引渡し前に、天災等により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を工事主管課長等及び受注者に通知しなければならない。
(監督員の出来形及び完成確認)
第22条 監督員は、部分払の対象となる工事部分の完了時及び工事目的物の完成直前に、受注者の立会いの上、出来形確認及び完成確認を終了した建設工事について、工事出来形検査請求書又は竣工届を受理することができる。
(検査)
第23条 監督員は、前条の規定により受理した工事出来形検査請求書又は竣工届に基づき、速やかに、監督員各自の担当部分の評定を行った成績評定書を工事主管課長に提出しなければならない。
2 工事主管課長は、橿原市建設工事検査規程第5条に規定する区分に応じ、検査依頼を行うものとする。
(監督の委託)
第24条 市長は、地方自治法施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督を行わせる場合は、この規程を準用する。
(適用除外)
第25条 当初の設計金額が130万円未満の工事は、この規程によらないことができる。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、建設工事の監督の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から実施する。
附 則(平成15年訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から実施する。
附 則(平成18年訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年訓令甲第8号)
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成22年訓令甲第20号)
この規程は、平成23年1月1日から実施する。
附 則(平成24年訓令甲第14号)
この規程は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日訓令甲第21号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成29年2月8日訓令甲第1号抄)
(施行日)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年2月12日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(令和7年3月12日訓令甲第6号)
1 この規程は、令和7年4月1日から実施する。
2 この規程の実施の際、現に改正前の橿原市建設工事監督規程の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
監督員区分表
設計額 | 1億5000万円以上 | 500万円以上1億5000万円未満 | 500万円未満 | ||||||
監督員区分 | 総括 | 主任 | 一般 | 総括 | 主任 | 一般 | 総括 | 主任 | 一般 |
職区分 | |||||||||
課長級(技術系) | ○ (*1) | ○ (*2) | |||||||
課長補佐級(技術系) | ○ | ○ (*2) | ○ (*3) | ○ (*5) | |||||
統括調整員(技術系)、係長級(技術系) | ○ (*4) | ○ (*3) | ○ (*4) | ○ | |||||
主査(技術系)、技師又は技術員 | ○ (*4) | ○ (*4) | ○ | ||||||
注1:(*1)の総括監督員の配置は、工事主管課長が必要と判断するとき上記区分表に従い課長級より1名を配置するものとする。
(*2)の総括監督員の配置は、工事主管課長が必要と判断するとき上記区分表に従い課長級又は課長補佐級より1名を配置するものとする。
(*5)の総括監督員の配置は、工事主管課長が必要と判断するとき上記区分表に従い課長補佐級より1名を配置するものとする。
なお、工事主管課長は、特に上記区分表の総括監督員の配置の有無にかかわらず総括監督員の権限を有し、必要な業務に当たるものとする。
注2:(*3)の主任監督員の配置は、上記区分表に従い課長補佐級、統括調整員又は係長級より1名を配置するものとする。
注3:(*4)の一般監督員の配置は、上記区分表に従い統括調整員、係長級、主査、技師又は技術員より1名以上を配置するものとする。
注4:工事主管課長が、上記区分表に定める監督員区分に該当する職区分の職員が課に配置されていない等の場合は、上席の職区分の職員を配置(兼任も含む)することができる。